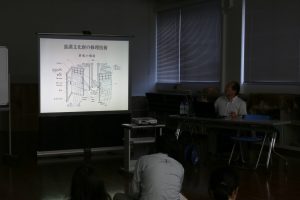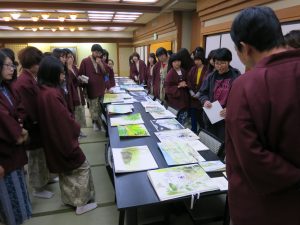半田昌規氏による、課外講座「装こう文化財の劣化損傷」が開かれました!
10月9日(月)に、半田昌規氏(株式会社半田九清堂代表取締役・国宝修理装こう師連盟理事)による課外講座「装こう文化財の劣化損傷」が開かれました。
今回の講義内容は、紙、木、絹など、劣化しやすく弱い素材で構成されている日本の文化財の修理技術「装こう」についてです。聴講に来た学生には装こう技術とその材料についてまとめられたプリントが配布され、講義では貴重な文化財を修理していく上での一連の流れや、詳しい修理方法、素材の調査についてスクリーンに映された情報とあわせてわかりやすく解説していただきました。文化財の修繕現場の他ではあまり聞くことの出来ない内側の話ということもあり、日本画学科に限らず他学科からも学生が多く集まりました。
一昨年、去年から続く全3回の半田昌規氏による文化財修繕技術に関する講義も、第3回目となる今回で最後を迎えました。半田先生、大変有意義な課外講座をありがとうございました!